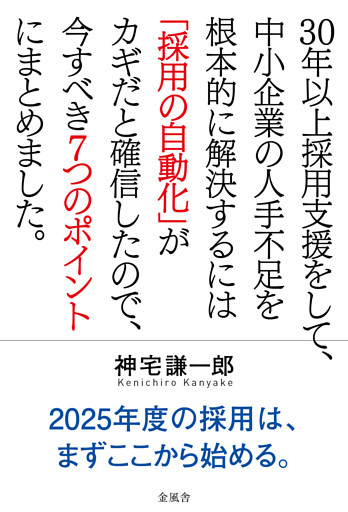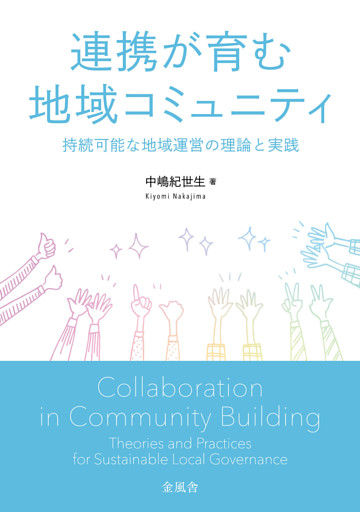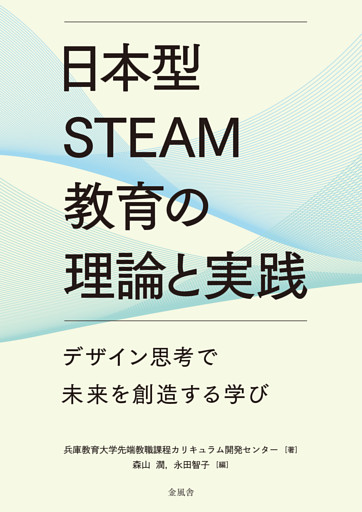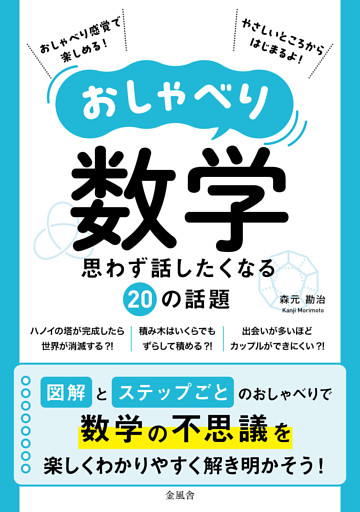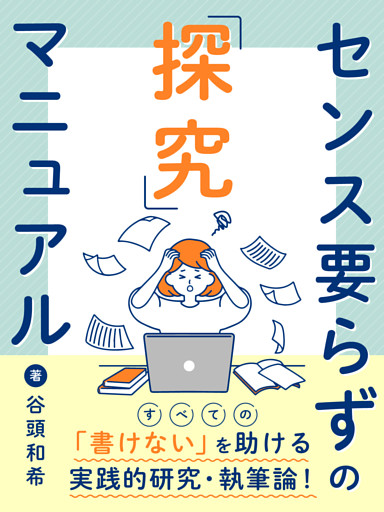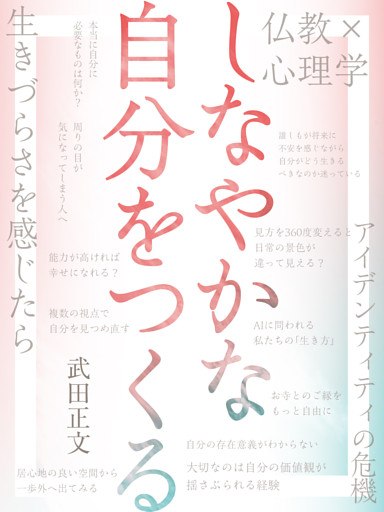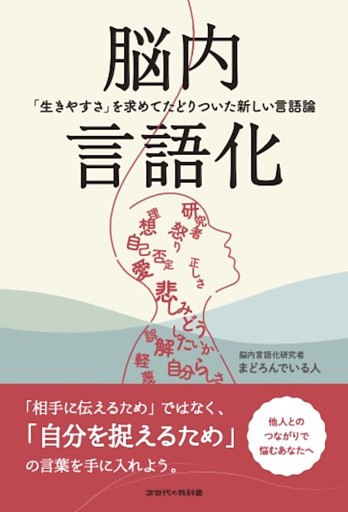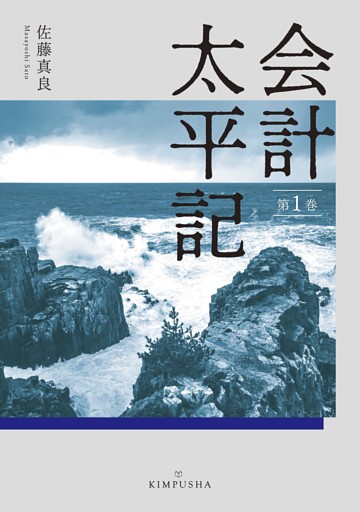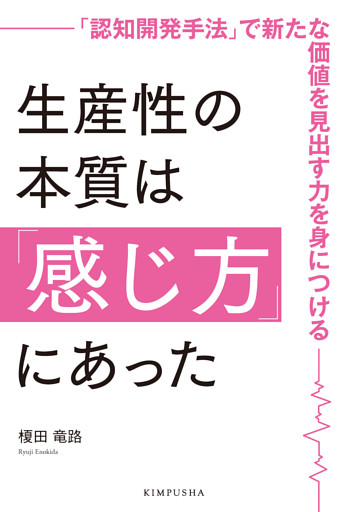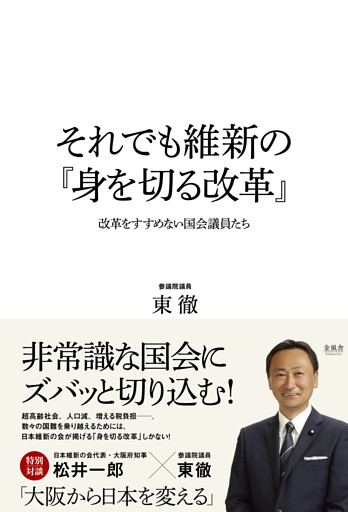-
30年以上採用支援をして、中小企業の人手不足を根本的に解決するには「採用の自動化」がカギだと確信したので、今すべき7つのポイントにまとめました。
人手不足に悩む中小企業の採用担当者へ。この本を読めば、中小企業の人手不足を解決するために今絶対に必要な「採用の自動化」という手法を「楽に」「簡単に」「自分たちの力で」行えるようになります。30年以上、採用トレーナーとして全国の中小企業をサポートしてきた著者が痛感したのは、多くの企業が、採用活動をサポートする便利なツール(自動化ツール)の存在やその活用方法を知らないこと。そして、そのせいで採用がうま
-
連携が育む地域コミュニティ :持続可能な地域運営の理論と実践
変容する地域社会における、新たな地域づくりの可能性本書は、宮城県大崎市岩出山地域でのフィールド調査をもとに、人口減少や高齢化、都市部への人口流出といった深刻な課題に直面する地域社会において、持続可能な地域運営の新しいかたちを探る実践的研究である。なかでも、著者自身が伴走した「臥牛プロジェクト」に代表されるような、多様な主体がゆるやかに関わり合う「場」の形成とその意義に着目し、地域のなかにおける「公
-
日本型STEAM教育の理論と実践:デザイン思考で未来を創造する学び
STEAM教育とは、Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics の 5 つの領域を重視した、世界中で期待を集める次世代型の教育モデル。文理融合と教科横断的な学びを促進することで、子どもたちの創造力と問題解決力を育むことを目指す。 本書は、兵庫教育大学が日本の学校教育に向けて開発した日本型STEAM教育「J-STEAM」の理論と実践を紹介。
-
おしゃべり数学 思わず話したくなる20の話題
数学をもっと気楽に楽しむことができたら。易しいところから、なるほど!と思えるところまで、ちゃんと理解できたら。優しく楽しく教えてくれる先生がそばにいたら。そんな声を受けて書かれたのが本書です。数学が苦手な人でも、おしゃべりを通して、必ず数学に興味が沸き楽しめます。また、数学の得意な人は、数学の面白さを、再発見すること間違いありません。先生と2人の生徒が、数学のいろんな話題を題材におしゃべりを展開し
-
センス要らずの「探究」マニュアル
「何も書くことがない」「アイデアはあるけど形にならない」「情報収集が難しい」……レポートやリサーチにつきものの悩みを解決する、超実践的執筆論!どんなテーマでも面白く、楽しく書くためのテクニックが詰まった、誰でも「探究」ができるようになるための一冊。
-
しなやかな自分をつくる 仏教×心理学で見えてくる自分らしさのヒント
「仏教×心理学」、2つの視点で探る「自分らしさ」とは。現役僧侶でカウンセラー、YouTuberでもある著者が「仏教×心理学」という独自の手法で、自分らしさを探るヒントを提案。生き方、アイデンティティに悩むすべての人たちへ。さあ、答えのない現代を生き抜く「しなやかな自分」を見つけよう!
-
あ、そのマンガ、違法かも。 「なんでも無料時代」のあなたに知ってほしいこと
意外と身近な違法コンテンツ。意図せず、または安易に、違法な道に迷い込まないために。漫画原作者でもある弁護士に聞く、違法コンテンツの基礎知識と行動すべきことが詰まったインタビュー録。
-
格闘家 アントニオ猪木 ─ファイティングアーツを極めた男─
アントニオ猪木はプロレスにおける”特異点”だった!”燃える闘魂”アントニオ猪木。その足跡があまりに大きく、かつ色濃すぎるが故に、事実とはかけ離れたファンタジーや伝説の類があたかも事実のように語られ、半ば歴史が〝捏造〟されてしまうリスクをはらんでいる。本書は、その強さと技術の源流と進化を、猪木自身の言葉で解き明かすことで「アントニオ猪木の強さと格闘技術のリアル」を後世に遺す、前人未踏・空前絶後、完全
-
「推し活疲れ」脱出記
楽しかった推し活が、他人の目を気にしているうちに「推し活疲れ」になってしまった。ミニマリズムを取り入れて、自分軸の心ときめく推し活をしよう!オタク系ミニマリストが提案する、自分の「好き」を大切にした推し活実践集。
-
やってみなよ、変わるから! 元スタイリスト、現フォトグラファー、未来映画監督
本書は、世間的には「負い目」と考えられるシングルマザーになっても、自分のやりたいこと、ワクワクすることを追いかけてづけ、前向きに自分の人生を楽しみ続けている著者のフォトエッセイだ。執筆のきっかけは主婦友達へのアドバイス。シングルマザーって大変じゃないの?そんな言葉に対して彼女は意気揚々とこう答える。「シングルマザーって面白いよ!」「何かしたい気持ちはあるけど勇気がない」「本当にそれでいいのか悩んで
-
うわの空のすすめ 自分が見つからない人のための現代川柳案内
若干20代ではやくも句集を商業出版するなど、現代川柳界のホープとして活躍めざましい暮田真名。彼女の作る句は、ユーモラスでありながら「その手があったか」と膝を打ってしまうような、言葉の新しい側面や面白さを見せてくれる。そんな川柳の極意を追求し続ける彼女は、いったいどんな人生を辿ってきたのか。そして、川柳の面白さはどこにあると考えているのか。本書では、「古めかしく時代遅れ」「なんだかパッとしない」とい
-
500人以上の無名の人にインタビューしたら人生変わった。
なぜ人は有名無名という肩書や知名度にこだわってしまうのか?本書は、ブログサービスnoteで3年間にわたり500人以上の一般人へのインタビューを続けてきた著者が辿り着いた「人という教科書」への考察を綴ったノンフィクション・エッセイだ。SNSを介して他人の活躍やきらびやかな人生を覗き見ることが自然になった現代。しかし、知名度や目立った肩書を持った人だけが本当に「教科書」となるべき立派な人なのだろうか。
-
脳内言語化
本書は、幼い時から言葉と向き合い続け、40歳手前にして自分なりの「生きやすさ」をつかみ始めた、「脳内言語化研究者」のエッセイと研究レポートです。 著者の研究テーマである「脳内言語化」とは、自分の心の中の曖昧な感情や思考を、「伝わるかどうか」を意識す
-
会計太平記第2巻
昭和終期から令和にかけての日本企業の会計報告をとりまく事件や動向から、どんな企業行動が行われたかを考察、紹介し、そこから日本経済の来た道への省察を行います。さらには、日本経済や企業文化まで考察を波及させ、従来の企業会計本の殻をやぶりたいという思いで綴った意欲作です。
-
会計太平記第3巻
昭和終期から令和にかけての日本企業の会計報告をとりまく事件や動向から、どんな企業行動が行われたかを考察、紹介し、そこから日本経済の来た道への省察を行います。さらには、日本経済や企業文化まで考察を波及させ、従来の企業会計本の殻をやぶりたいという思いで綴った意欲作です。
-
会計太平記第1巻
昭和終期から令和にかけての日本企業の会計報告をとりまく事件や動向から、どんな企業行動が行われたかを考察、紹介し、そこから日本経済の来た道への省察を行います。さらには、日本経済や企業文化まで考察を波及させ、従来の企業会計本の殻をやぶりたいという思いで綴った意欲作です。
-
いつのまにか自分の幸せは、マルチにとって都合のいい幸せに書き換えられていた
マルチ商法による被害が後を絶たない。特に近年では若者の被害件数が全体の半数近くにまで増加し、せっかく内定をもらった企業(合格した大学)を辞退する、入ったとしてもすぐに会社(大学)を辞めるといった取り返しのつかない選択をしてしまう人もいる。なぜ若者はマルチ商法の標的とされやすいのだろうか。それは、若者の多くはマルチ商法の詳しい実態や勧誘された場合の対処法を知らないからである。公教育の場では、未だマル
-
生産性の本質は「感じ方」にあった:「認知開発手法」で新たな価値を見出す力を身につける
「考え方ではなく感じ方を変える」本書は、私たちの感じ方の正体である「知覚」の領域に着目し、物事の本質を見抜く力を高めるためのトレーニングを行う、認知開発手法の入門書です。著者・榎田竜路は、メディアプロデューサーとしてこれまで多くの映画や映像の制作に携わってきました。一万人以上の様々な人たちに取材を重ねる中で気づいたことは、私たちの新しい価値を生み出す力の低下が日本の生産性の低さの原因ではないかとい
-
それでも維新の『身を切る改革』 改革をすすめない国会議員たち
本書では、参議院議員の東徹が、地方議員出身者の立場私から見た、国会の理不尽な「非常識」について深く切り込んでいく内容となっています。日本維新の会が掲げる「身を切る改革」が、なぜ、今の日本に必要なのか、国会議員の無駄遣いを多くのデータから紐解いて、大阪から日本の未来を変えていく戦略を分かりやすく解説しています。
-
クライアントが喜べば、士業は儲かる 「本物」の情報を発信する、これからの時代にあるべき士業
現在、日本にコンビニが何軒くらいあるか、ご存知ですか?大手のチェーン店を合わせると、全国に約4万3000軒以上あると言われています。そして、その数と同じくらいあるのが、行政書士事務所です。士業は国家資格ですが、業界は飽和状態です。独立しても、新たな価値を生み出さなければ淘汰されます。「資格を取って独立はしたけれど、生活が成り立たない」「資格を取ろうと勉強しているけれど、今後が不安……」しかし、有難
- 1
- 2
並び替え/絞り込み
並び替え
ジャンル
作者
出版社
その他